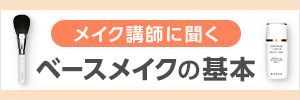はるか昔から存在する「美」の概念。平成の30年間ではどんな美しさが生まれ、何が美しいとされていたのでしょうか――。
当企画「平成の美」では、さまざまな角度から「美」を追及するため、インタビューを実施。「平成」という時代を振り返りながら、もはやひとことでは言い切ることのできない「美しさ」について聞いてみました。
平成は、スクリーンのなかにも美しさが求められるようになった時代
平成の30年間で、私たちを取り巻くテクノロジーは劇的に進化しました。iモードサービスの開始、カメラ付き携帯電話の発売、スマートフォンの登場、SNSの普及…。
ぱっと思いつくだけでも象徴的なできごとがたくさん。テクノロジーの変遷とともに、世のなかの「美」の価値観も確実に変わってきた気がします。
「大きな枠組みでいうと、平成はディスプレイのなか、スクリーンのなかにも美しさが求められるようになった時代だと思います」
そう話す鈴木康太さんは、日本最大のテクノロジー情報サイト「GIZMODO JAPAN(ギズモード・ジャパン)」の編集長。iPhoneをはじめとする最新プロダクトや、デジタル社会の”いま”を読み解くニュースを発信し続けています。

「それまでもテレビとか、目の前で鑑賞する演劇やライブでは、普通に美しさが表現されていました。でも平成になってみんなが自分の携帯電話を持ちはじめると、その表現の場が自分のスクリーンになるんです。
しかもテレビのように一方的に受け取るのではなく、自分で発信するようになり、スクリーンのなかで自分を他人にどう見てほしいかという意識が生まれてきた。それは、美意識ととても近いんじゃないかなと思います」
――それは1999年にiモードサービスが開始されてからでしょうか?
「iモードの前もあったけど、本当にみんなに根付いたのはiモードが発売されてからですよね。
僕は当時中学生でしたが、まずメールがすごく流行りました。昔のガラケーの絵文字って、単色で人が笑っているアイコンとか、赤いぐるぐるとか、黄色いキラキラとか。いまみたいにリッチじゃないんだけど、絵文字の使い方に、たぶんすごく人柄が出ていた。
『この人、絵文字たくさん使うんだ』とか、『対面で話すときよりテンション高い!』とか。そういうところにも、美意識って出るじゃないですか」

――デコメールとか、HTMLメールも人気でしたよね。
「そうそう。いまはiPhoneが出てきて、写真の撮り方ひとつでもガラケー時代とは比べ物にならないくらい表現の幅が広がりましたよね。いろいろなフィルターを使ったり、スタンプを押したりして、アプリで写真を加工する文化もできました。
目の前で起きたことの記録として撮るんじゃなくて、自分の記憶と気持ちを画像に込める。インスタはとくに、みんな気づかないうちに自分のセンスを反映させていると思います」
――ということは、いまインスタを使いこなしている人は、かなり美意識が鍛えられていると言えそうですね。
「そうだと思います。自分の気持ちにあった写真をポストする技術ってあると思うんですよ。そういうクリエイティブな力が高い人ほど、いまの世界はコミュニケーションしやすい。『いいね!』やコメントがたくさんついたり、フォロワーが増えたり…。
インフルエンサーとまではいかなくても、『この人、きっと楽しい人で、人気者だろうな』と思わせるだけでも、大きな力になります」
機能性×美しさを兼ね備えたiPodの衝撃

――平成のガジェットで、鈴木さんがとくにハマったものはありますか?
「ガジェットというと言葉に色がつきすぎるけど、ひとつ挙げるとすればiPodです。それまで実用性ばかりだった電気が通るプロダクトに、初めてみんなが分かる形で美意識を持ち込んだのがAppleだと思うんです。
くるくる回るクイックホイールだけで、画面上にあんなにきれいでリッチなメニューが出てくるなんて、当時はなかった。
機能性をつきつめたら、見た目も美しくなっていく。そういうプロダクトができたのはiPodからで、そこからiPhoneやiPadが生まれた。その美しさは言わずもがなです」
――プロダクトの造形美を変えた、Appleの存在は大きかったですよね。
「そうですね。『Appleがすべてを変えた』なんて言うとコピーみたいだけど、それは変えられない事実。だからみんな、こんなに好きなんだと思います」
コスメと同じかも。プロダクトの物語を楽しみたい

2017年に、ちょうど30歳でギズモードの編集長になった鈴木さん。最新テクノロジーを扱うメディアというと、コスメを愛する@cosmeのユーザーとは距離があるように思えるけれど、「じつは共通点がある気がする」と話します。
「ギズモードはよく『ガジェットメディアです』と紹介されるんですが、ちょっと違和感があるんです。ひとことでいうと、イノベーティブ(革新的)なもの、イノベーションのストーリーを追うメディアだと思っていて。
僕らの場合、ただ新作だからうれしいんじゃなくて、いろんなイノベーションのストーリーを知ったうえで手にしているから、なんだか物語を手にしているような気分になるんです」
――たしかにそのうれしさは、私たちが新しいコスメを買うときの感覚と似ているかも。ブランドやメイクアップアーティストのファンだと、新作の登場にさらにテンションが上がります。ストーリーを追い続けているからこその楽しみがありますよね。
「そう、映画とかドラマのように見てきているから、余計に楽しい。たとえばiPhoneXが出たときに、『ホームボタンがなくなった!』ということに対して、すごい物語性を感じちゃうわけです」
――ホームボタンに…?
「ホームボタンは、ずっとiPhoneのアイデンティティだったんですよ。スマホが出はじめたころは、難しくてこんなの使えるかと言われていた。そんな時代に、Appleは“押すだけでいつでもホーム画面に戻れる”ボタンを作りました。おかげで、みんながスマホを使えるようになった。
視覚障がいがある方も、あのホームボタンがあることで『いつでもホーム画面に戻ってこれる』という安心感があるんだそうです」
――本当にイノベーティブなデザインだったわけですね。
「はい。そんなホームボタンを、iPhoneXでAppleが自ら取り払うってものすごいストーリーなんです。この10年でiPhoneが、一部の人から世界中のみんなのものになり、誰でも使いこなせるようになったということ。それだけですごくドラマティックに思えます」
テクノロジーも“心の時代”へ

最後に鈴木さんに、今後どんな「美しさ」を持ったテクノロジーを期待しているのか聞いてみました。
「いま、ジャンルを問わずに注目され始めているのは、『身体性に還る』ということ。手紙や雑誌、人と目を合わせて話すことの良さ。人間の肉体を使ったコミュニケーションや活動の気持ちよさ、充実感が見直されるようになってきています。
これを受けて、テクノロジーにも“心の時代”がくるんじゃないかと感じています。考えてみると、こんなに技術が進化したのに、注目されるのは機能やスペックといった陽の部分ばかり。もっと陰の部分というか、人の精神的な疲れとか、ちょっと参っているときに寄り添ってくれるようなテクノロジーを、みんなが求め出していると思うんです。
象徴的なのが、2018年末に登場した『LOVOT(らぼっと)』です」
YouTube
「LOVOTはキャラクター性のあるロボットで、2体セットで58万円くらい。昔のロボットって、『ご主人さま』とかいって、人間を手伝ってくれるイメージがありましたけど、この子たちは何もしない、ただそこにいるだけ。言葉も話しません。でも、彼らに触るとあったかいんです」
――体温があるんですね。
「そうです。体のあらゆる動きに高度なテクノロジーがつまっていて、目のデザインも一体一体違っていて、本当にコミュニケーションしているように振る舞うから、人間の脳は彼らを“社会性を持つ生き物”だと錯覚してしまうんです。
まったく役に立たないけど、この子がいると心が和む。しかも、放っておくと2体で勝手にコミュニケーションしだすんですよ」
――それは、かわいすぎますね…!
「実際にデモンストレーションでLOVOTと遊ぶと、それまで興味がなかった人も夢中になります(笑)。最先端の人の心に寄り添うテクノロジーで、しかも日本の企業が作っている。これからも注目していきたいと思っています」

抱っこするとずっしり重く、温かくてかわいい「LOVOT」。まさに平成の終わりに生まれたロボットが、「人を癒す」というテクノロジーの新たな美を見せてくれそう。
そして「人を癒す」という点では、コスメもロボットも同じなのではないかと感じました。

鈴木 康太さん
ギズモード・ジャパン 編集長
1986年、山梨県生まれ。2010年、株式会社メディアジーン入社後、株式会社インフォバーンを経て、2011年よりギズモード・ジャパンに加入。多くのブランデッドコンテンツを手がけ、2016年4月より副編集長。2017年7月、編集長就任。

取材・文/田邊愛理