には「まゆ玉飾り」をご利用者さんと作り、飾ります。
私が本格的に?気になりだしたのは娘の保育園時代から!
その時は本物の米粉で作ったのだけど、レクではNG ...
なので職場では、本物の枝に軽量紙粘土で「まゆ玉」に模
した物を作るのだけど、昨年は例年以上に盛り上がり「大
成功」だったので、今年も張り切ってやっちゃいます。

ちなみにこちらがその時の作品の一部。
チープな出来ですが、なんか味わいがあるでしょ?!
・:*:・.・:*:・.・:*:・.・:*:・.・:*:・.・:*:・
□ おまけ(過去)日記
○ 保育園で「まゆ玉飾り」に参加してきました。
「まゆ玉飾り」とは、枝に紅白のお餅等を飾り小正月
(こしょうがつ)に、それを食べ祝う行事らしいです。
園では他に園児の歌や先生方のお芝居などがあり、
お昼はママさん達の「手作り焼きそば」・「お汁
粉」も食べたし!! 本当に楽しかったです♪
ヽ( *⌒¬⌒*)ノ *☆。.:*:・’゜
記:10/01/16
・:*:・.・:*:・.・:*:・.・:*:・.・:*:・.・:*:・
□ 餅花(もちばな)

餅花(もちばな)は、お正月(とくに小正月に)ヌルデ・エノキ・ヤナギな
どの木に小さく切った餅や団子をさして飾るもの。一年の「五穀豊穣(ごこ
くほうじょう)を祈願」する予祝(よしゅく)の意味をもつとされています。
左義長(さぎちょう)の行事で飾ったり、食べたりする地方も多いようです。
東日本一帯に広がるものに繭玉(まゆだま)があります。
米の粉をカイコの繭のかたちにして木にさしたものです。
養蚕(ようさん)に関連の深い道具などをいっしょに飾る地方もあります。
カイコの安全を祈願したものですが、これも餅花(もちばな)の一種です。
小正月が終わる頃にもぎとり焼いて食べます。
・:*:・.・:*:・.・:*:・.・:*:・.・:*:・.・:*:・
□ まゆ玉飾り
(上に記したように ... ) 全国それぞれ形式は色々ですが、東日本を中
心にした地方では、旧暦で最初の満月に当たる01月15日を、 01月01日
の「お正月」に対して「小正月(こしょうがつ)」と呼び、農作業や養
蚕(ようさん)に関係する、昔からの伝統的な行事が残されています。
「まゆ玉」は、紅白に染めた米の粉や餅を丸めてミズキ・ヤナギ・
エノキなどの枝に餅をいくつも付け、豊作や商売繁盛・家内安全・
長寿健康を願って神棚や大黒柱や天井に飾る「伝統行事」です。
※ 呼び名に違いはあれ、意図するものは双方同じようです。
・:*:・.・:*:・.・:*:・.・:*:・.・:*:・.・:*:・
□ 日本一の「まゆ玉飾り」
○ 新潟県の道の駅「阿賀の里」楽市じぱんぐの「まゆ玉」飾り

(2008年)イベント用に店内に大木を運び入れて「まゆ玉」で装飾した
もの。 高さ13.5m・横50cmの日本一の「まゆ玉飾り」なんだとか?!
ちなみにマンションで考えると、(1フロア当
たり約3mで換算すると)約5階に相当します。

売店にも「まゆ玉」と縁起の良い「まゆ玉飾り」が♪
最近は個人の家では柱が無くなって、門松も、
団子の木も縛ることが出来なくなりました。
ですが昔からの日本の文化なので、馴
染みがなくても何だかホッとします。
しかもこちらは粉を練って作ったのではなく、全部「お餅」な
んだそうです!!さすが米どころ「新潟」ならではですねぇ♪
小正月の繭玉飾り世田谷の伝統行事
イベント:日々の雑記帳:So-netブログ - せつこ
・:*:・.・:*:・.・:*:・.・:*:・.・:*:・.・:*:・
※ 以下は「管理用」ですので、スルーをお願い致します。 n(u u*)n
○ 七福神 (しちふくじん)
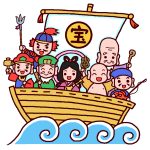
七福神とは、福をもたらすとして日本で信仰されている
「七柱の神」です。おめでたい存在、縁起物とされます。
一般的には以下の七柱の神とされます。
○ 恵比寿 (えびす) 日本の土着(ど‐ちゃく)信仰
大国主命(おおくにぬしのみこと)の御子(みこ)と伝えられていて、
「大漁追福(たいりょうついふく)」や「商売繁盛」や「五穀豊穣」
をもたらす、漁業や商業や農業の神様です。智恵を働かせ体に汗を流
して働けばこの神が福財(ふくざい)を授けるという信仰の神様です。
※ 古くは 「大漁追福」 の漁業の神であり時代と共に福の神として
商売繁盛や五穀豊穣をもたらす、「商業や農業の神」となりました。
○ 大黒天 (だいこくてん) インドのヒンドゥー教
インドのシヴァ神と日本の大国主命(おおくにぬしのみ
こと)の神仏習合(しんぶつしゅうごう)の神様です。
有福・食物・財福・出世のご利益があるとされています。
印度の神様で仏教の守護神ですが、日本では有福
・福徳を示し商売繁盛の守り神として有名です。
※ インドのヒンドゥー教のシヴァ神と日本古来の大国主命の習合
です。大黒柱と現されるように食物・財福を司る神となりました。
○ 毘沙門天 (びしゃもんてん) インドのヒンドゥー教
インドのクーベラ神で、四天王の一人多聞天と
も言われ、日本では毘沙門天と呼ばれています。
宝塔とやりを持ち悪霊を退散させ財宝をさずけるといわれ、戦いの神・鎮護国
家の神と信仰され福を与える神様です。毘沙門天を信仰すると十種の福を得る
とされ、その中には無尽の福・長命の福・勝軍の福・愛敬の福などがあります。
○ 弁才天 (弁財天) (べんざいてん) インドのヒンドゥー教
美と智恵と音楽・財運と弁舌と芸術の神と知られ、七福神の中
の紅一点の女神です。インドの神話で「サラスヴァティー神」
と呼ばれ、蛇を従え 財や富をもたらす女神とされています。
上野不忍池、近江の竹生島、安芸の厳島、江ノ島の弁財天など有名
ですが、すべて「水」にかかわりのある場所に建てられています。
※ 七福神の中の紅一点で、元はインドのヒンドゥー教の女神であるサラスヴァ
ティー神です。七福神の一柱としては「弁財天」と表記されることが多いです。
○ 福禄寿 (ふくろくじゅ) 中国の道教
頭長の福禄寿は道教の神様で、一羽の白鶴を伴う南極星
の化身だとも言われます。福徳・人徳・長寿の神様です。
※ 道教の宋の道士または、道教の神で南極星の化身
の老子である寿老人の別名または同一神とされます。
○ 寿老人 (じゅろうじん) 中国の道教
白ひげの寿老人は、三千年の長寿を保つ玄鹿をしたがえ 人々の難を祓う団扇を
持つ 天南星または寿星の化身だといわれます。健康、長寿、幸福の神様です。
※ 道教の神で南極星の化身の老子です。
○ 布袋 (ほてい) 中国の仏教
唐の時代に実在したといわれる仏教の僧や弥靭菩薩
の化身だといわれます。開運・良縁・子宝の神様です。
・:*:・.・:*:・.・:*:・.・:*:・.・:*:・.・:*:・
□ 予備知識
・ 五穀豊穣 (ごこくほうじょう)
穀物などの農作物が豊作になることを幅広く指す言葉。
「五穀」は米、麦、粟、黍(きび)または稗(ひえ)、豆の5種類の穀物のこと。
※ 「豊穣(ほうじょう)」は、作物などが豊かに実ること。
・ 予祝 (よ‐しゅく) ・・・ あらかじめ祝うこと。前祝い。
・ 予祝儀礼 (よしゅくぎれい)
農耕儀礼の一。新春の耕作開始に先立ち、主として小正月にその年の豊
作を祈って行う前祝いの行事。田打ち正月・田遊びなどの類。予祝行事。
・ 左義長 (さぎちょう)
小正月に行われる火祭りの行事。地方によって呼び
方が異なる。日本全国で広く見られる習俗である。
記:16/01/12
・:*:・.・:*:・.・:*:・.・:*:・.・:*:・.・:*:・
16/01/01:(oё)/ 1月「今日は何の日?」INDEX ☆彡:2016年
01/01:金 (oё)/ 我が家の「01月」まるっと INDEX(2016年)☆彡
16/01/14:木 (oё)/ 今年もやります「まゆ玉」作り ☆彡
仕事・(勇退)送別会(ぷちプレ):晴れ
※ こちらは職場ネタとして「ビジネス・マナー」に登録させて頂いております。
あと、ただいま明日の大役仕事の資料作りに励んでおります。よってコスメと
は関係のない記事ばかりなのですが ... ご了承頂きたく存じます。m(_ _*)m



