
各季節の始まりの日(立春・立夏・立秋・立冬)の
前日のことを指す言葉だったそうです。つまり節分
とは「季節を分ける」ことをも意味しています。
ただ江戸時代以降は、特に立春(毎年2月4日
ごろ)の前日を指す場合が多くなりました。
新暦では2月3日。旧暦では大晦日にあたり、新年を迎えるた
めに邪気や厄病を祓う行事として執り行われていたようです。
節分の習慣は、古代中国で行われていた大晦日の行事が奈
良時代に伝わり、宮中の年中行事になったとされています。
現在のような豆まきの風習は、室町時代以降に始
まり、江戸時代頃より一般庶民にも広まりました。
「臥雲日件録(がうんにっけんろく)〔瑞渓周鳳(ずいけいしゅうほう)〕」
によると、1447年(文安4年)に「鬼外福内」を唱えたと記されています。
近代、上記の宮中行事が庶民に採り入れられたころから、節分当日の
夕暮れ、柊の枝に鰯の頭を刺したもの「柊鰯(ひいらぎいわし)」を
戸口に立てておいたり、寺社で豆撒きをしたりするようになりました。
一部の地域では、縄に柊やイワシの頭を付け
た物を門に掛けたりするところもあります。
臥雲日件録(がうんにっけんろく)・ 瑞渓周鳳(ずいけいしゅうほう)
・:*:・.・:*:・.・:*:・.・:*:・.・:*:・.・:*:・
□ 恵方巻き (えほうまき)
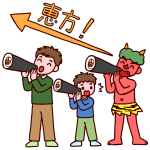
恵方巻きとは、節分にその年の恵方を向いて食べると縁起が良いとされる太巻き。別
名、丸かぶり寿司、恵方寿司、吉方巻きとも言われます。大坂の船場で商売繁盛の祈
願をする風習として始まったものといわれますが、正確な起源は分かりません。
○ 恵方巻きの食べ方って?
恵方巻の食べ方は、その年の恵方の方角に向かって、切らずに、無言で祈りな
がら少しずつ食べる。切らないのは「縁を切らないように」ということだそう。
どうして巻き寿司なの? それにどんな7種類?
恵方巻きに使う、のり巻きの中の具材は7種類と言われてい
ます。この7種類という数字はどこからきているのかと言う
と、七福神(しちふくじん)に由来すると言われています。
七福神とは、七つの神様の総称で七福神を参拝すると7つ
の災難が除かれて、七つの幸福を授かると言われています。
ちなみに七つの神様とは、1.大黒天(だいこくてん)、2.毘沙門天(びしゃも
んてん)、3.恵比寿天(えびすてん)、4.寿老人(じゅろうじん)、5.福禄
寿(ふくろくじゅ)、6.弁財天(べんざいてん)、7.布袋尊(ほていそん)と
なります。良く「宝船」乗った神様の絵がありますが、あの神様たちです。
この七福神にあやかり、例えば、「キュウリ・しいたけ・玉子焼き・うなぎ・で
んぶ・かんぴょう・えび」などの7種類の具材をのりで巻くわけですが、こうす
ることにより、「7品巻いて生活に幸せを巻き込む」ということだそうです。
七福神の信仰自体は室町時代まで遡るといわれますが、恵方巻きとのかかわ
りは定かではなく、恵方巻きの風習の成立自体も詳細は定かではありません。
とにかく良いもの・縁起の良いものに「あやかる」という庶民
の気持ちが風土となってこのようになったものと思われます。
神仏への信仰についても、「~といわれている」というのみ
で、出典(文書の裏付け)の定かでないものは多くあります。
恵方巻き 7種類の具材と七福神
・:*:・.・:*:・.・:*:・.・:*:・.・:*:・.・:*:・
□ 福豆(ふくまめ)

節分の豆まきでまく炒り豆のこと。 炒った豆を歳神に供えたあと、年男
(家では家長)が、「鬼は外、福は内」と唱えながらまき、まかれた豆を
年の数(もしくはプラス一個)だけ拾って食べ、一年の無病息災を願う。
もともと穀物や果物には「邪気を祓う霊力」があると考えらていることから、大
豆を炒って福豆として用いられていました。 最近では、豆まき後の掃除が簡単
だからと、落花生や袋入りの豆が福豆の変わりに用いられているようです。
「12ヶ月のきまりごと歳時記」2月の歳時記
○ 素朴な疑問 〔節分は落花生?大豆?〕
こちらによると、節分豆の地域性については、北海道および東北地方、新潟県内
は落花生が優勢、長野県内においては、大豆の家庭と落花生の家庭が混在、関東
地方においては、特に茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県といった北関東地方を中
心に大豆が優勢、東海地方以西においては大豆が優勢と考えられるとのことです。
節分の豆の種類に落花生?驚きの豆も!みんなの豆事情を調査

ちなみに我が家は埼玉県ですが、「落花生」をまいて「福豆」を食べます。
・:*:・.・:*:・.・:*:・.・:*:・.・:*:・.・:*:・
□ 柊鰯 (ひいらぎいわし)

立春前の節分の夕暮れ、季節の変わり目に生じる邪気を祓うために門戸に
さす、柊の枝と焼いた鰯の頭のこと。鰯の臭いに誘われた鬼の目を柊の葉
の棘で刺す!あるいは鰯の生臭さは邪気を祓う、ともいわれています。
「土佐日記」の元日の項には、 「柊の枝となよし(ぼら)
の頭をさした注連縄を思い出す」との記述があるそうです。
「12ヶ月のきまりごと歳時記」2月の歳時記
・:*:・.・:*:・.・:*:・.・:*:・.・:*:・.・:*:・
16/02/01:月 (oё)/ 2月「今日は何の日?」INDEX ☆彡:2016年
16/02/03:水 (oё)/ 節分の豆は「落花生」?「大豆」?
※ 今日は何の日?は、職場ネタとして「ビジ
ネス・マナー」に登録させて頂いております。
いつも「足跡」を、本当にありがとうございます!!
忙しい時ほど、励みになっております☆彡 n(U U*)n




コメント(0件)
※ログインすると、コメント投稿や編集ができます