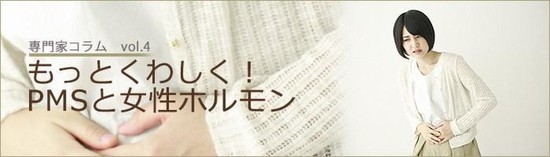
こんにちは! PMSマニア編集部の管理栄養士石川です。
みなさん、PMS(月経前症候群)についてニュースなどでも最近耳にされ、既にご存知の方も多いと思います。今回は、PMS(月経前症候群)と女性ホルモンの関係についてお伝えします。
■PMS(月経前症候群)とは
PMSとは、Premenstrual Syndromeプレ・メンストラル・シンドロームの略です。「月経前症候群」と呼ばれています。月経前の3~14日の間に起きる心と体の症状で、月経が開始すると治まるのが特徴です。症状としては、頭痛やめまい、吐き気、腰痛、ニキビが出来る、イライラ、精神的不安などがあります。原因は脳内のホルモンの異常、ビタミンB6低下など挙げられますが、特に女性ホルモンの分泌量の変動が関与すると言われています。

■女性ホルモン
いわゆる「女性ホルモン」は、卵胞ホルモン(エストロゲン)と黄体ホルモン(プロゲステロン)のことを指します。
卵胞ホルモン(エストロゲン)
基礎体温を下げる働きがあります。自律神経や、感情の動き、骨、皮膚、脳の働きにも大きく関係しています。妊娠に備えて子宮の内膜も厚くします。
黄体ホルモン(プロゲステロン)
基礎体温を上げる働きがあります。体内の水分保持や、食欲増進の動き、皮脂分泌を促して肌を保湿するなどの働きがあります。そして、妊娠後の妊娠継続の働きをします。
■女性ホルモンの分泌
女性の月経周期はおよそ28日周期で、月経期、卵胞期、排卵期、黄体期の4つの時期を繰り返しています。
ホルモン
卵胞ホルモン(エストロゲン)
・月経中には分泌量が最も少ないです。
・排卵の直前に分泌がピークに達します。
・排卵期には少し減少して、排卵後二つ目のピークを迎え、妊娠が成立し なければ分泌は極端に減少します。
黄体ホルモン(プロゲステロン)
・月経から排卵するまでは、ほとんど分泌されません。排卵後から月経までの2週間で、徐々に分泌が増えていきます。
・妊娠が成立しなければ、黄体ホルモン(プロゲステロン)は必要なくなります。分泌が極端に減少していき、排卵前のレベルに戻ります。
■PMS(月経前症候群)と女性ホルモンの関係
2つの女性ホルモンは、月経の周期により分泌量が変動しています。まだ詳しくは解明されていませんが、これがPMS(月経前症候群)の原因の一つだと言われています。また、黄体期にPMS(月経前症候群)の症状が出ていることから、排卵後に分泌される黄体ホルモン(プロゲステロン)が影響しているのではないかと言われています。
■PMS(月経前症候群)の対策
PMS(月経前症候群)は、ストレスや緊張、疲労が蓄積されると、症状が強く現れやすくなります。ですので、ストレスを解消しリラックスできるように工夫しましょう。また、睡眠時間を確保することや体を温めることもおすすめです。




コメント(0件)
※ログインすると、コメント投稿や編集ができます