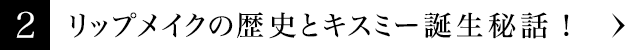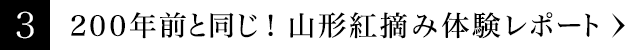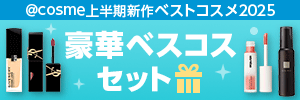![Chapter.3 200年前と同じ!山形紅摘み体験レポート[@cosme NIPPON PROJECT]](https://cache-cdn.cosme.net/media/cur-contents/file/image/201708/72254b9bcfc0bfea66740fdcd936237b.png)
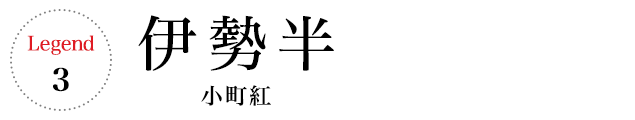
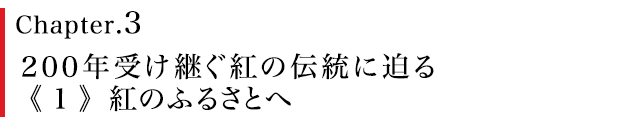

高品質なプチプラのコスメを販売する一方で、伊勢半は江戸時代と同じ製法で今も“紅”を作り続けています。伊勢半の“小町紅”に使われているのは、紅花の産地として名高い、山形県産の紅花。第三章と第四章では、200年続く紅作りの技法をお届けします。

今回お邪魔したのは、山形県南部にある白鷹町。山形県紅花生産組合連合会副会長・今野正明さんの紅花畑です。紅花の栽培及び、伝統的な紅の加工法の保存に尽力しています。

紅花は「夏至から11日目の半夏生の日にぽつんと最初の1輪が咲き、翌日から畑中の花が咲く」と言われています。実際に最初の花が咲くと一気に開花が進み、7月上旬には畑一面が黄色に…!
花摘みは早朝、まだ日が昇りきらないうちに、全て手作業で行います。これは太陽が昇ると朝露でしんなりとしていたとげが乾燥して、たってしまうため。朝4:30起床でいざ紅花畑へ!

紅花にはとげがあるため、畑に入るときは長袖と革製のグローブを着用します。つぼみが開いたばかりでも、赤くなりすぎても、良質な赤の色素は抽出できません。人の目で根もとがほんのり赤く色づいた紅花を選び、花びらをそっとつまんでキュッとひねるように、ひとつひとつ摘んでいきます。



ほんの数分作業を続けと、みるみるグローブが黄色に!昔は手のひらを紅花の黄色と、とげでにじんだ血の色に染めながら素手で花摘みをしたといいますから、本当に大変な作業ですね。

白鷹町全体で約6ヘクタールの紅花畑があるそう。1年のうち約2、3週間、しかも手作業で摘まなくてはいけないため、この時期は周囲の人総出で花摘みをします。黙々と作業すること2時間、2kgの紅花が収穫できました!


摘んだ紅花は、乾燥させた“紅餅”(べにもち)へと加工します。
まずは花びらを井戸水にさらして、葉っぱや虫などをていねいに取り除きます。これを荒振(あらぶり)といいます。最初に紅花の9割以上を占める黄色い色素が流れ出します。

不純物を取り去った紅花を、井戸水でさらしながら揉み込んでいきます。これを中振(なかぶり)といいます。花の表面に細かな傷をつけ、酸化反応を促進させる行程。井戸水を使うのは、水道水だとアルカリに傾いてしまうためです。

花びらのふかふかした感触が気持ちいい!周囲には植物の青々とした香りが立ちのぼります。花びらに含まれるオイル成分のおかげで、手のひらもしっとり。この中振のあと、仕上げの揚振、そしてしばらく時間をおいて酸化・発酵を進めます。

朝・昼・晩と1日に3回水を打ち、花びらをひっくりかえしながら3日〜5日ほどたつと…。見事な赤色に!写真左上が初日、右下が酸化・発酵が終了した紅花です。黄色い紅花にたった1%しか含まれない赤の色素は、こうやって取り出していくんですね。

酸化・発酵が終わった紅花を臼と杵で“餅状”につきます(現在は電動餅つき機を使用)。写真は今野家に保存されている臼と杵。紅花の色で赤く染まっています。

(©Ryoichi Toyama)
つき上がった餅状の紅を丸めてぺたんと押しつぶし、むしろの上に広げて、表裏をひっくり返しながら天日干しします。江戸時代の最盛期は、この紅をひっくり返すために出羽三山詣での行者や参拝者の手を借りたそう。

上の写真は完成した“紅餅”。1枚に約300輪の紅花を使用し“赤の色素を凝縮した”紅餅は、江戸時代は高額で取引されたとか。
今回の体験で驚いたのは、紅花の収穫や加工が、200年前とまったく同じ方法で行われていたこと(変わったのは竹かごがプラスチックに、臼と杵が電動餅つき器に進化したことのみ!)。こうして手間ひまかけて完成した紅餅は、紅職人の手に渡り、美しい化粧紅へと姿を変えるのです。