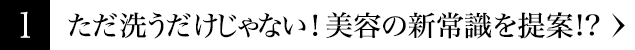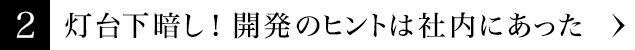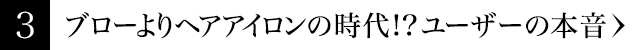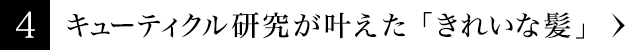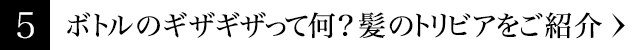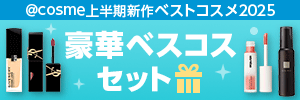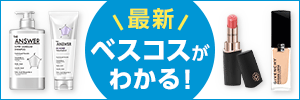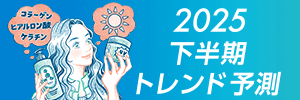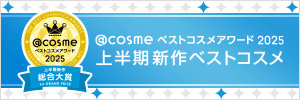![Chapter.5 「エッセンシャル」トリビア[@cosme NIPPON PROJECT]](https://cache-cdn.cosme.net/media/cur-contents/file/image/201807/3290412bb3fa557d47ac187c12ba5109.png)

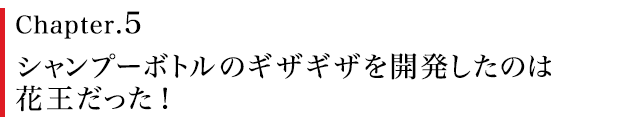
ヘアのことなら花王に聞け!今回は髪事情のあるある雑学をご紹介。まずは、シャンプーボトルのギザギザ、あの意味をご存知ですか?
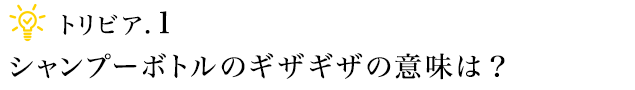

「お風呂でコンタクトを外していても、また目をつむっていても、シャンプーとコンディショナーを識別しやすいように開発しました。盲学校にもご協力いただき、誰もが触っただけで識別できるよう、試行錯誤の上に生まれたデザインです」と教えてくれたのは花王の商品広報・俵紀子さん。
見慣れたデザインは花王初のデザインだったんですね。
Q:ギザギザの誕生秘話を教えて!
「シャンプーとコンディショナーを間違えてしまう、というお客さまのお声が相談センターに数多く寄せられていたことがきっかけです」(俵さん)というのも興味深いお話。お客さまの声を実際に形にした、というのは何だか嬉しいですね。
Q:オリジナルデザインやロゴなどは今や特許を取るのが当たり前ですが、このデザインは取得しなかったのでしょうか?
「1991年に一度は特許を取得しましたが、広く社会に広める必要性があると考えたことから、特許を取り下げることにしたんです」(俵さん)。
このエピソードは驚き!なかなか知られていないですよね。
「消費者が混乱しないよう、業界全体にデザイン統一を働きかけたことで、現在日本ではほとんどのシャンプーに同様の刻みが入れられています」(俵さん)。
へぇ〜、ギザギザのデザインにはこんな話があったんですね。
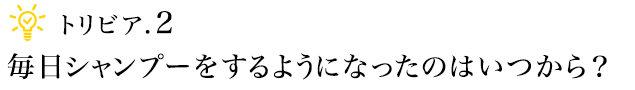

洗髪の歴史は先ほども触れましたが、リンスやコンディシナーの歴史は意外とあやふやなモノ。商品広報の俵さんに聞いてみたところ、1965年に「ヘアーリンス 花王テンダー」が花王初のリンスとして発売していたとか!
Q:リンスは週に1度でよかった? どのような仕様だったの?
当時のリンスは週に1度のお手入れで「ぬるま湯に溶かして使用する」という仕様で提案していたそう。
「今では信じられないとお思いの人もいるかもしれませんが、つい最近のお話なんですよ」(俵さん)
「リンスの効果効能として、毛髪の取り扱いを容易にする・毛髪の傷みをやわらげる・静電気防止作用を示す・毛髪がしなやかになりクシ通りがよくなる・パーマやセットが美しく仕上がる、などといった特徴を訴求していたようです」(俵さん)
また、週に1度のお手入れというのは、「当時の洗髪頻度が週に1〜2回であったことが理由だったようですね」(俵さん)
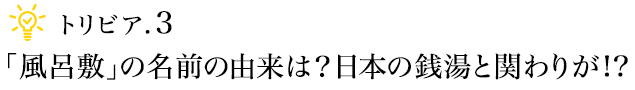

日本の洗髪事情に欠かすことのできない銭湯。この銭湯文化で生まれたものが「風呂敷」というのは案外知られていないみたい。風呂敷の由来について花王ミュージアムで調べてみました。
Q:日本の銭湯事情はいつから?
庶民が親しんだ銭湯文化は、江戸で発達し、多いときでは500軒以上の銭湯が営業していた様子。その後、明治以降全国に広がり、昭和40年代が銭湯のピークといわれ、全国で約18,000軒が営業していたといわれている。
Q:風呂敷はこうして生まれた!
いろいろな諸説があるのですが、「へぇ〜」と頷きたくなるエピソードをご紹介。
室町時代に時の将軍が風呂を設けて全国の大名をもてなした際、脱いだ着物を間違いないように家紋入りの袱紗にいれ、その上で身づくろいをしたといわれています。「風呂で使う敷物」、これが「風呂敷」のはじまりといわれています。江戸時代には庶民が風呂敷の中に着替えなどを入れ、銭湯へ通っていました。
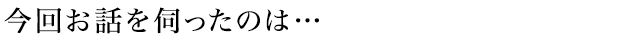
【丸田誠一(まるたせいいち)】
花王企業文化情報部・花王ミュージアム館長。花王ミュージアムの館長を2014年から務める。花王製品の紹介のみならず、日本の美容文化の変遷や現代人の生活習慣の歴史などを精力的に発信している。
【神谷光俊(かみやみつとし)】
花王 ヘアケア事業部 シニアマーケター。メンズのブランドマーケティングから販売部門を経て、2013年からヘアケアを担当。シンガポール支社に駐在後、エッセンシャルのブランド担当となる。
【渡邊俊一(わたなべしゅんいち)】
花王ヘアケア研究所 主任研究員。入社15年。大学院で修士課程を卒業後、2002年に入社。2014年からはエッセンシャルの担当となり、成分、処方開発を始め、髪への効果研究や消費者のヘアケア行動調査にも携わっている。
【中島詩乃(なかじましの)】
花王 ヘアケア事業部。大学卒業後、2015年に入社。ヘアケア事業部4年目。今回のエッセンシャルリニューアルプロジェクトに参加。
撮影/斎藤大地
取材・文/長谷川真弓