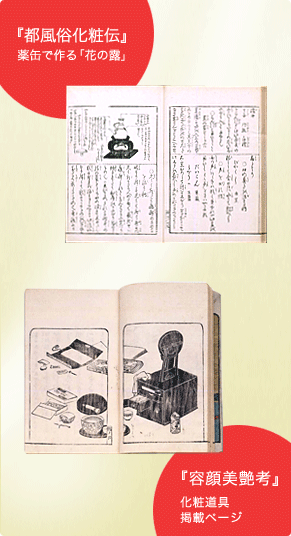 |
 代と同じように、江戸時代にもコスメが販売されていました。化粧水については、特に人気の高いベストコスメがあったことが分かっています。「花の露」という化粧水は、ロングセラー商品! なんと江戸前期から明治時代まで販売されていたんですよ。その人気は、江戸後期の美容雑誌に、類似品の作り方が紹介されるほど。美しくなるためには、手間を惜しまない江戸の女性像が想像できませんか? 代と同じように、江戸時代にもコスメが販売されていました。化粧水については、特に人気の高いベストコスメがあったことが分かっています。「花の露」という化粧水は、ロングセラー商品! なんと江戸前期から明治時代まで販売されていたんですよ。その人気は、江戸後期の美容雑誌に、類似品の作り方が紹介されるほど。美しくなるためには、手間を惜しまない江戸の女性像が想像できませんか?
それから、多くの人がこの化粧水を使うきっかけとなったのが、風呂屋など、人の集まるところに張り出される絵がありました。今でいうとポスターといったところ。美人が描かれているもので、その絵の中に商品を描き入れて、宣伝していたんです。
他には、滑稽本『浮世風呂』で有名な式亭三馬が販売していた、ガラス瓶入り「江戸の水」や、今でもお馴染みのヘチマの水で作られた化粧水「美人水(びじんすい)」などが人気がありました。
|
ここで気になるのは、メディアの数が少ない時代にベストコスメがあったその理由。当時の美容雑誌のひとつ、『都風俗化粧伝』を見てみると、その中で「花の露」の使用感を「顔の腫物(できもの)が癒やされて、白粉(おしろい)のノリがキレイ」と紹介。今でいうクチコミが残っているんですよ。「きれいになりたい」と願う美容意識の高い江戸時代の女性たちが、美容雑誌や広告のコスメ情報をチェックして、ベストコスメが誕生したんですね。
|
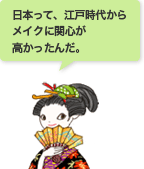 |
| 〔参考文献〕 『容顔美艶考』、『好色一代男』、『江戸の化粧品小間物店其他』 |